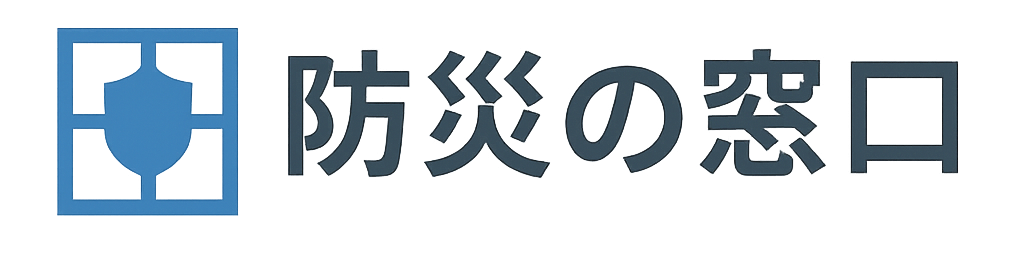どれほど備えていても、災害は突然やってきます。実際に災害が発生した時に「何をすればいいか」「どう動くべきか」を事前にイメージできているかどうかで、被害の大小や命運が大きく分かれます。このページでは、地震、台風、津波、火災など災害ごとの具体的な初動対応と、家庭での行動ルールづくりについて、実用的に解説します。
1. 災害別 初動マニュアル
【地震のとき】
- まず身の安全を確保する
- 頭を守り、机の下など安全な場所に避難
- 窓ガラスから離れる
- 外ではブロック塀や看板、ガラスの近くに近づかない
- 揺れが収まったら火の始末と出口の確保
- キッチンにいた場合は、余裕があればガスの元栓を閉める
- ドアが歪まないうちに玄関や窓を開けて脱出口を確保
- 避難判断
- 自宅に損傷がある、火災が発生した、津波警報が出た等の場合は避難
- 家族と合流してから行動(可能なら)
【津波が来るとき】
- 高台や避難ビルへすぐに移動
- 警報が発令された時点で即座に行動。海や川には絶対に近づかない
- できるだけ高い場所へ「垂直避難」
- 車移動は避ける
- 渋滞の危険や通行止めのリスクが高い
- 徒歩での避難が基本(高齢者などの事情がある場合は例外)
- 再警報に注意
- 津波は繰り返し襲ってくることがあるため、解除されるまで絶対に戻らない
【台風・豪雨】
- 事前に情報を確認し、外出を控える
- 気象庁や自治体の警戒レベルに注意
- 夜間や暗い時間帯に避難することは極力避ける
- 自宅で待機する場合
- 停電に備えてライトやモバイルバッテリーを準備
- 水害が想定される地域では、2階以上で待機
- 避難が必要な場合
- 避難情報が「避難指示」になったら速やかに行動
- 道路の冠水や土砂災害に注意
【火災が発生したとき】
- すぐに119番通報+家族の避難を最優先
- 初期消火は煙が薄い・火が小さいときのみ
- 炎が天井に届いていたら消火はあきらめて避難
- 姿勢を低くして煙を避ける
- 濡れタオルで口元を覆いながら、姿勢を低くして移動
- エレベーターは使わない
- 停電・閉じ込めの危険があるため、階段で避難
2. 要配慮者への対応
災害時には、高齢者・子ども・障がいのある方・妊産婦・外国人など、「要配慮者」への配慮が求められます。
高齢者・障がい者
- 介助が必要な場合に備え、家族や近隣との連携を事前に決めておく
- 福祉避難所の位置を確認しておく(通常の避難所とは別)
乳幼児・子ども
- 必要な物資(ミルク・おむつ・おやつなど)を常にバッグに
- パニックを防ぐため、抱きしめる・話しかけるなどの安心対応
外国人
- 多言語対応アプリや災害用多言語情報サイトの活用
- 地域でのサポート体制(多文化共生の防災体制)を把握
3. 避難所での生活と心構え
避難所は、安全を確保する場ですが、ストレスや不便も多い環境です。
必ず持って行きたいもの
- 防寒着、タオル、スリッパ、耳栓、目隠し用のアイマスク
- 貴重品と身分証のコピー(本人確認が必要な場面がある)
- 食物アレルギーがある人は、自分用の食料を別途準備
感染症対策
- マスク、アルコール消毒液、使い捨て手袋など
- 周囲との距離を保つ
- 換気やこまめな手洗いを意識
トラブルを防ぐためのポイント
- 貴重品や情報は自己管理
- ゴミ出しや清掃に協力する
- 無理な要求やクレームは控える
4. 災害後に気をつけること
被災後も、二次被害や健康被害に注意が必要です。
- 余震への警戒:壊れかけた建物は危険、できるだけ近づかない
- 水・食品の安全:断水直後の水道水、非常食の賞味期限などを確認
- 詐欺・悪徳商法:修理業者やボランティアを装った詐欺に注意
- 心のケア:PTSDや不眠が続くようであれば、早めに相談機関へ
まとめ
災害が発生したとき、最も大切なのは「慌てない」「正しい情報を得る」「早めに動く」ことです。災害ごとの正しい行動を知っておくことで、大切な命を守る力になります。家族と一緒に定期的にこのマニュアルを見直し、災害への備えを行動レベルに落とし込んでおきましょう。